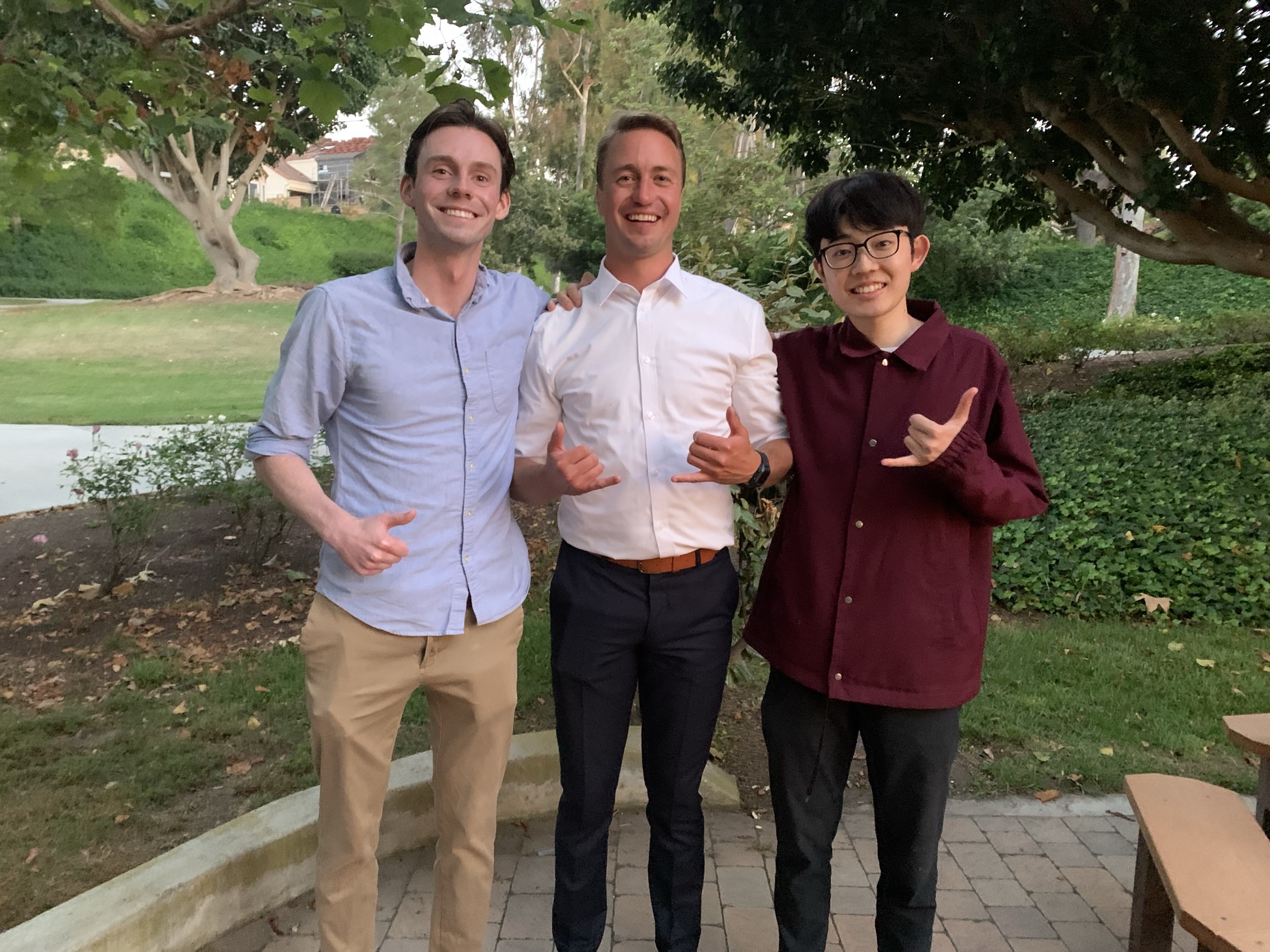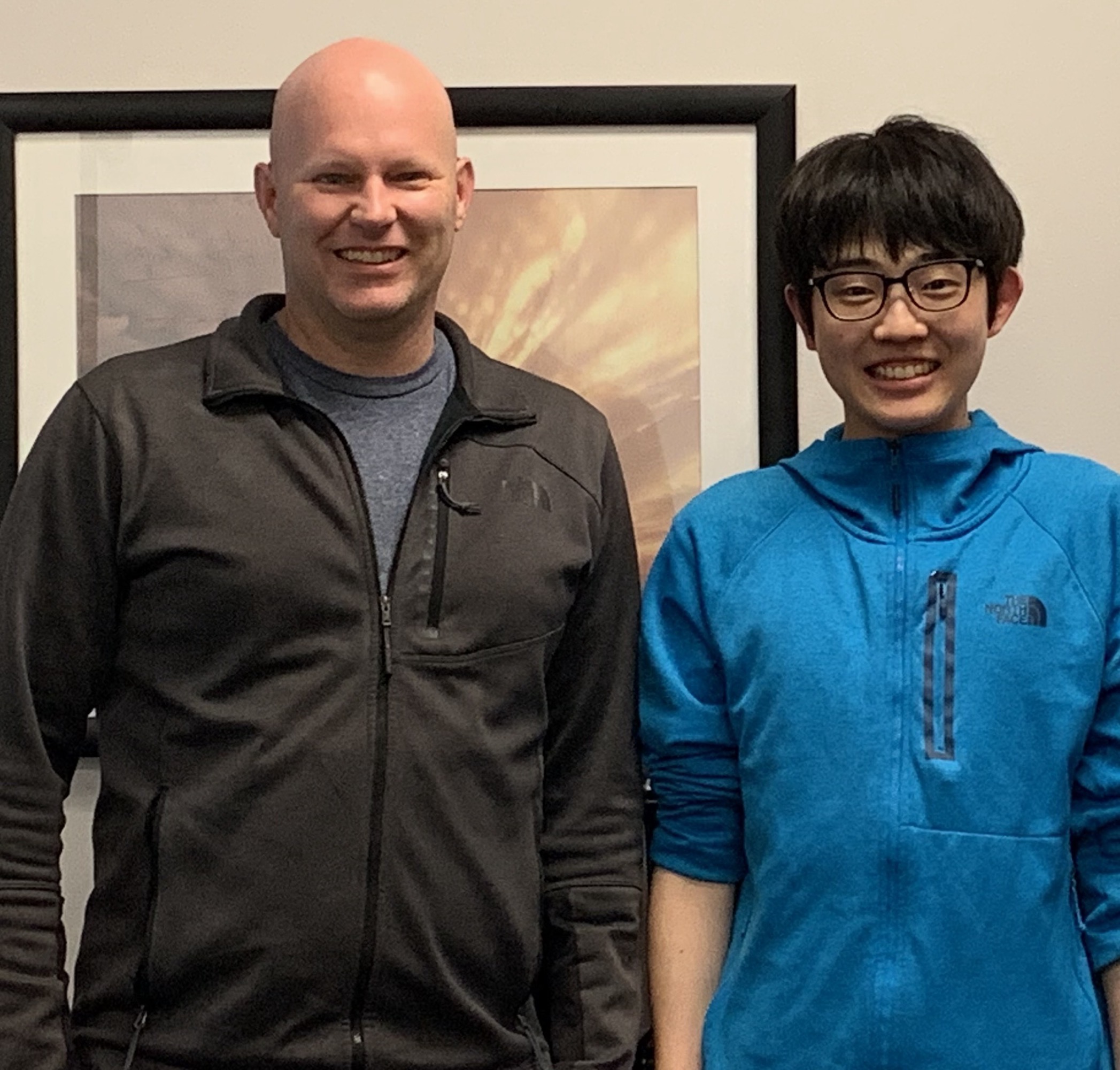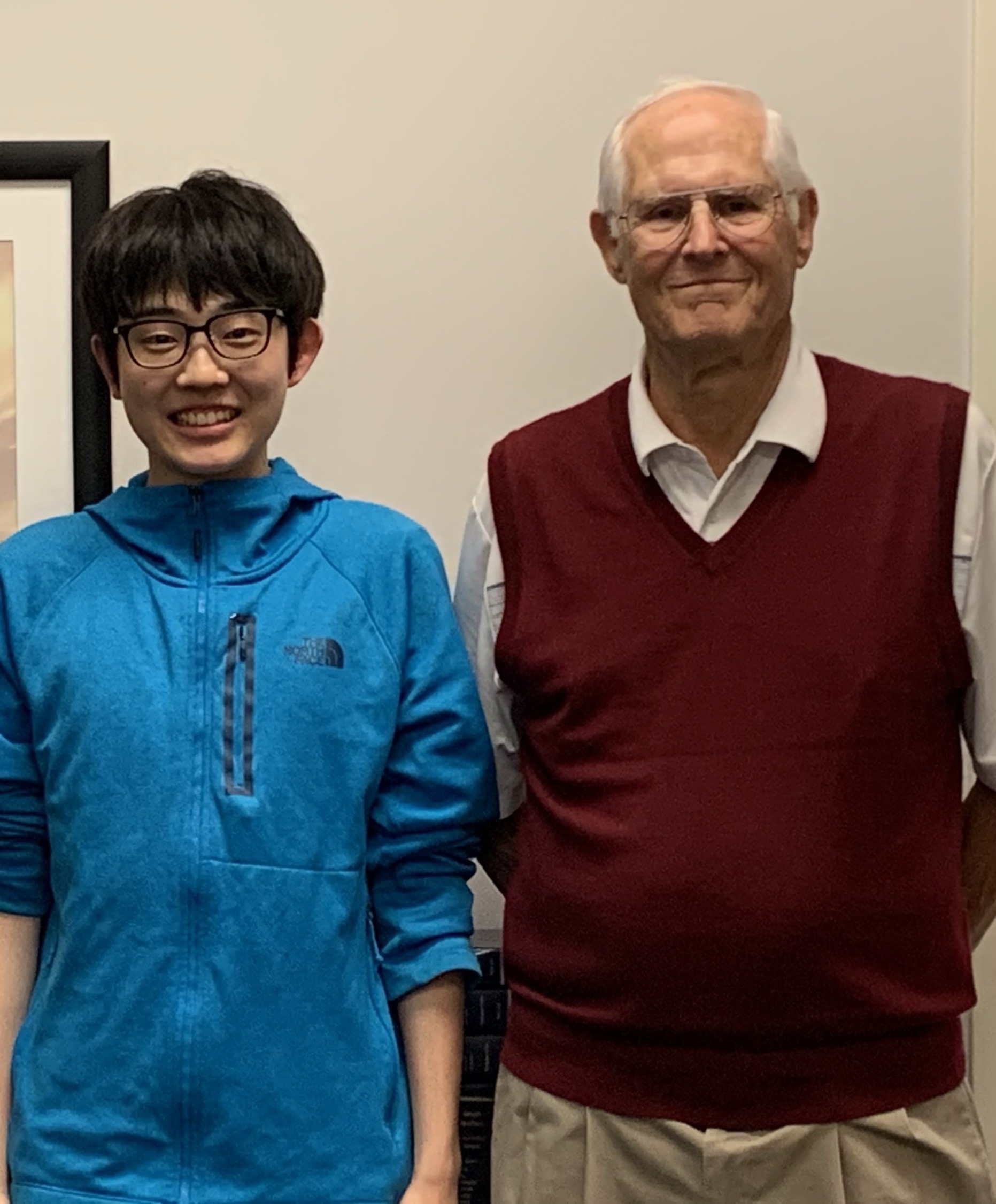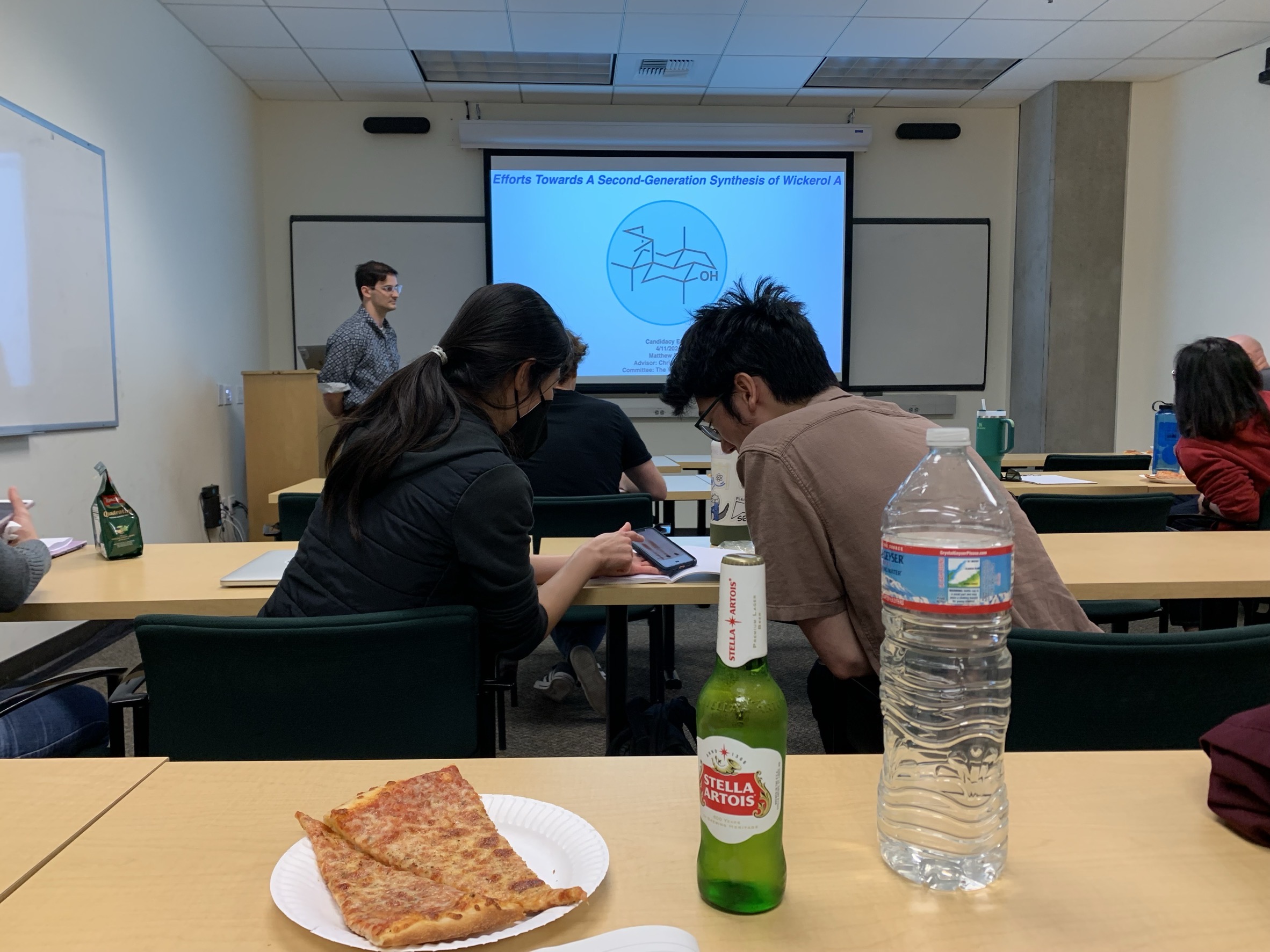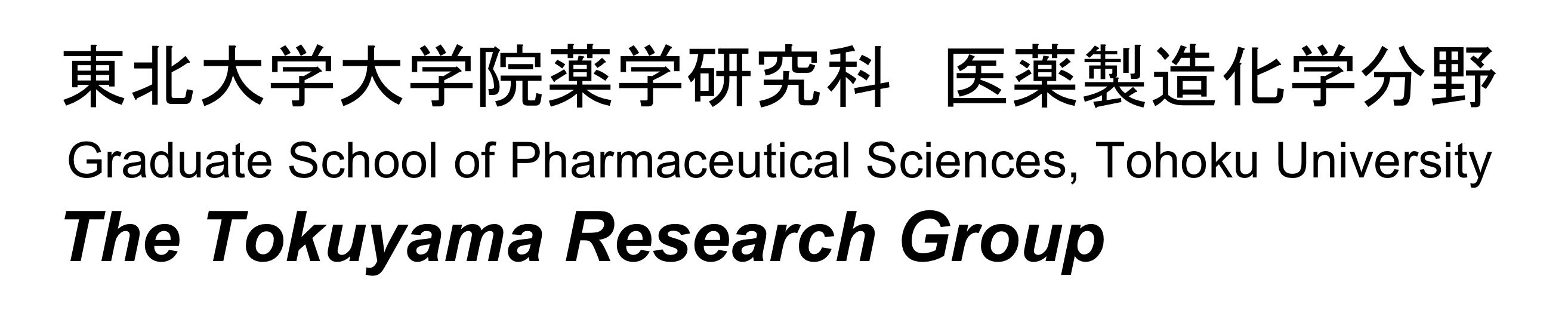
University of California, Irvine (Prof. Christopher D. Vanderwal)
2024年4月1日~6月30日 DC2 河野 駿
この度、私は、カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)のChristopher D. Vanderwal教授の研究室に三ヶ月間留学する機会をいただきました。UCIは10あるカリフォルニア大学システムのなかで比較的歴史が浅い新興の大学ながら、研究力に強みをもつ気鋭の大学と位置付けられています。また、在米大学ながら学生の中でアジア人が最も多い点やマスコットキャラクターとしてアリクイ(anteater)を設定するなどユニークな特色もあります。今回お世話になったVanderwal教授が主催する研究室は、新規方法論の開発および複雑天然物の全合成研究を中心に研究されています。さらに近年は、ケミカルバイオロジーに関する研究にも取り組まれております。今回私は、セスタテルペン類(5分子のイソプレンからなるC25を母骨格とする天然物)の全合成研究に携わりました。今回の留学にあたり、旅費・滞在費の一部を東北記念開発財団および日本学術振興会に支援していただきました。
留学に至るまで
異なる環境で研究し自身の環境適応力を高めるとともに、世界最先端の研究に直接触れたいと考えていた私は、D1だった2023年より徳山教授に留学を打診しました。米国の合成化学研究者との交流を希望したところ、親交のあったVanderwal教授をご紹介いただき、アポイントメントを取ってくださいました。Vanderwal教授からはすぐに快諾の返事をいただき、その後、大学事務とのやり取りやオンライン面談を経て正式に留学が決まりました。渡米まで約半年あったため、滞在先の選定や東北記念開発財団への申請準備などを、余裕をもって行うことができました。
留学先の研究室での様子
Irvineは米国でもトップクラスに治安が良い地域として知られ、日没後も注意を払いながら外出できました。そのため、日本にいる時と同様に朝9時頃から夜10〜11時まで研究室に滞在し、実験に集中できました。徳山研究室では1人1テーマが基本ですが、Vanderwal研では複数人で1つのテーマに取り組むことも多く、私も3人チームの一員としてセスタテルペンの全合成に取り組みました。チームで研究をするのは初めてでしたが、密なコミュニケーションを通じて良い連携が生まれ、最終的にフラグメント合成と鍵反応であるフラグメントカップリングまで到達し、研究の発展に貢献できたことは大きな経験となりました。隔週で7〜8人のサブグループによるVanderwal教授との研究報告会が行われ、英語でのディスカッションは当初緊張から言葉が詰まりましたが、次第に慣れて堂々と対話できるようになりました。
観光
滞在先は渡米前に民宿サイト「Airbnb」で見つけた4人でのルームシェアでしたが、入居から1か月後に屋根の雨漏りが発覚し、急遽退去を求められるというトラブルに見舞われました。一週間で新しい滞在先を探す必要がありましたが、なんとか見つけることができました。休日は研究室の友人と天文台やレストランを訪れたり、野球観戦を楽しみました。研究室外での会話は日常的な英語表現やスラングを学ぶ良い機会となりました。
留学を通じて感じたアメリカと日本の違い
初めにVanderwal教授とメールでやり取りをしていたとき、「北米ではPIをファーストネームで呼ぶのが一般的だから、私のこともChrisと呼んでいい」と言われたことに驚きました。日本では「〇〇先生」と呼ぶのが普通であり、初めは少し緊張しながらChrisと呼んでいました。また、日本では講座制が一般的ですが、米国では独立したPIが研究室を単独で運営するのが一般的で、その分ポスドクの存在感が非常に大きいと感じました。ポスドクはPIからの信頼も厚く、実験のアドバイスや指導だけでなく、プレゼンや論文執筆に関しても学生を広くサポートしており、日本との違いを強く実感しました。加えて、「他人は他人・自分は自分」と考えている人が多く、日本人ほど他者への干渉は大きくない印象でした。
留学を通じて感じたこと
私が今回の留学で特筆したい学んだことは積極性の大切さです。共同研究者のLucasとSeamusはそれぞれ英国人と米国人でした。欧米人は黙っていても話しかけてくれると勝手にイメージしていましたが、決してそのようなことはありませんでした(当然人によります)。そのため、受け身になるのではなく、自分から積極的にとにかく話しかける姿勢がとても大切だと感じました。互いの伝えようとする気持ちと理解しようとする気持ちが噛み合えば意思疎通は可能です。もちろん言語の壁があり、うまく伝えられない恥ずかしさが纏わりつきます。しかし、その恥ずかしさこそが、英語力・コミュニケーション力を減退させる毒となることを強く実感しました。英語ネイティブは世界人口に比べたら圧倒的少数派なことを意識して、決して恥ずかしがらずに思い切って話しかけにいく姿勢が密なディスカッションを生むことができることを学びました。今後もそのような姿勢と英語力を磨き続け、世界を相手に活躍できる研究者を目指していきます。
最後になりますが、今回の留学準備中・期間中に多くの方々のご支援をいただきました。快く受け入れてくださったVanderwal教授、日々温かく接してくれた研究室の皆様、特に共同研究者のLucasとSeamusには研究面で多大なご協力をいただきました。また、この機会を与えてくださった徳山英利教授に厚く御礼申し上げます。
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|