
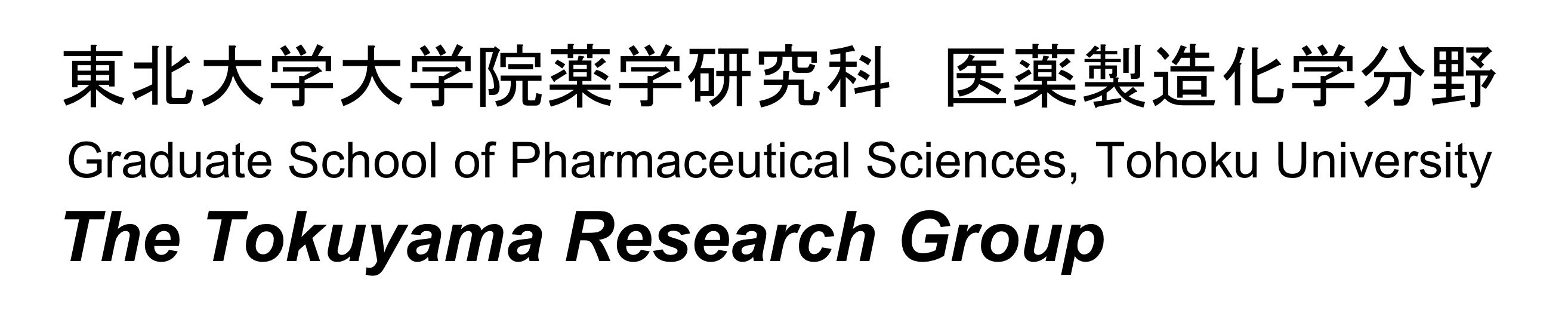
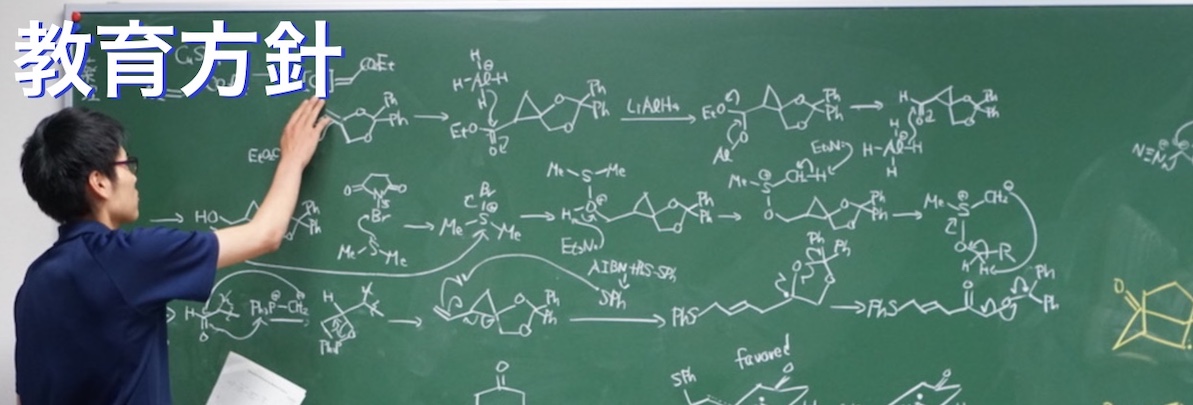
当研究室では、どのような化合物でも自らのアイデアで合成経路を立案し、試行錯誤しながら実際に合成を成し遂げる力のある自立した合成化学者の育成を目的として、日々の研究教育活動を展開しています。そのためには、広範な有機化学に関する知識と論理的な思考能力、実験技術をバランスよく養成することが大切であると考えています。教科書や論文から既存の反応や合成に関する知識を得ることは言うまでもなく、反応機構の解析を基に新たな合成反応や合成経路を考え、反応条件改良のヒントを得る能力は、新規化合物を合成するために欠かせません。また、化合物の構造的な特徴から反応条件や後処理の方法を適切に選択する能力も、紙の上のプランを実践に移すのには必須であり、これらは日々の経験から感覚として身に付ける以外にないと考えています。
我々のグループでは合成化学者としての最低限必要な知識と思考能力を身に付けるために、グループミーティングの中で色々なプログラムを行っています。その中のいくつかを紹介すると、まず、週に一度反応機構の問題演習を行い、3ヶ月ごとにそれらの中からいくつかの問題を選択して試験を行っています。これは、海外の大学院で行われているCumulative Examinationの制度を模倣したもので、これにより、予想外の反応が進行した場合の反応解析力や、化合物の反応性を基にした合成経路の立案能力を養うことを目的としています。また、月に一度、決められた化合物の合成経路を提案しメンバーの評価を仰ぎます。さらに、プレゼンテーション能力とディスカッション能力の向上を目的として、数ヶ月に一度、研究の進捗状況を学会形式で発表しています。ある程度の結果がまとまれば、国内の様々な学会で発表を行います。また、博士後期課程の学生には国際的な視野を身につけるため、在学中に国際学会での発表をして欲しいと考えています。さらに、1-3カ月程度、海外の大学において研鑽を積むことを奨励しており、これまで在籍した学生の半数以上が実際に短期研究留学しています(詳細は本ページの下を参照して下さい)。
このような研究を進めるためには、身につけて欲しい研究者としての素養があります。まず、研究室は一つの小さな社会ですので、社会人としての常識的な行動が要求されます。さらに、我々のグループでは、日々のディスカッションを大切にしています。黙々と実験するだけではなく、スタッフとはもちろんのこと、周りの学生とも積極的にコミュニケーションを取り、自己を高めて行く意欲が必要です。また、実際に行う反応の大部分は、データベースにも無くだれも試したことのないものばかりですので、予想通り進行することは稀です。まさに、研究とは失敗の中にわずかなヒントを見つけて壁を乗り越えていくことの繰り返しだと言えます。そこで、幾多の失敗にもめげずそれらを受け入れて、なぜ失敗したのかを考察し、問題点を克服する粘り強さがきわめて重要です。最後に、絶え間ない好奇心と日々の実験を継続して行えるだけの心身の自己管理能力が最も大切であることを付け加えます。
グループミーティングについて
当研究室では有機化学に関する幅広い知識と論理的な思考能力の習得を目的として、火曜日と金曜日の夕方にグループミーティングを行っています。また、配属一年目の学生を対象に、土曜日午後に全合成の論文紹介、月・火・木・金曜日の夕方にスタッフによる講義・演習(朝ゼミ)を通じて、基礎的な有機化学の定着を行っています。火曜日(18-21時) |
・ 最新の全合成や方法論に関する論文紹介(毎週) |
金曜日(18-21時) |
・ 研究発表(毎週) |
不定期(13時-15時ごろ) |
・ 全合成の論文紹介(毎週) |
月・火・木・金曜日(夕方) |
・ スタッフによる講義・演習 |
海外研究機関での研究留学について
当研究室の博士課程学生には、博士1年又は2年次に、外国の研究機関で1-3カ月程度の研究経験を積むことを奨励しています。
多くの場合は、研究テーマは派遣先のテーマです。場合によっては、この期間の仕事が論文になる人もいます。これまでの派遣先と
指導教員を以下に示します。また、主にPOSTECH(韓国・浦項工科大学)から大学院生が来訪して、数カ月の研究経験を積んでいます。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
海外学会報告
Campus Asia Program Summer School (2014)
Gordon Research Conference (2016)
International Symposium on Pure & Applied Chemistry 2017 (2017)
International Symposium on Pure & Applied Chemistry 2018 (2018)
The Third A3 Roundtable Meeting on Asia Chemical Probe Research Hub (2018)
11th Singapore International Chemistry Conference (SICC-11) (2022)
卒業後の進路
| 学部卒 | H18年度 東北大学病院薬剤部 1名 その他全員修士課程進学 |
| 修士卒 | H18年度 博士進学1名 就職2名(三菱化学、ゼリア新薬) |
| 博士卒 | H18年度 博士研究員1名(理化学研究所),就職2名(武田薬品工業、大沢薬局) H21年度 就職1名(東北大学薬学部) H22年度 就職1名(アステラス製薬) H23年度 就職2名(アステラス製薬、大塚製薬) H24年度 就職3名(第一三共、興和、小野薬品工業) H25年度 就職3名(田辺三菱製薬、塩野義製薬、アスビオファーマ) H26年度 就職3名(東レ医薬研究所、旭化成ファーマ、ケミクレア) H27年度 博士研究員1名,就職2名(JT、杏林製薬) H28年度 就職3名(塩野義製薬、日本新薬、金剛化学) H29年度 就職2名(協和発酵キリン、花王) H30年度 就職4名(三井化学アグロ、東和薬品、昭和電工、第一三共) H31年度 就職1名(武田薬品工業) R03年度 就職1名(中外製薬) R04年度 就職1名(大塚製薬) R05年度 就職2名(中外製薬、石原産業) R06年度 就職1名(大鵬薬品工業) |
Last Updated December 11, 2014