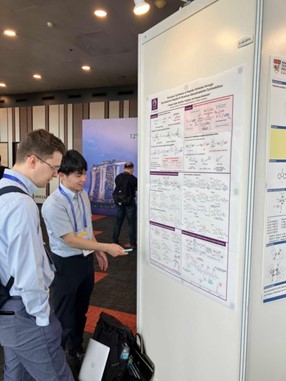令和6年度齊藤記念薬学教育研究支援基金成果報告
- 分子設計化学分野
- 博士課程前期2年の課程 2年次
- 岩田 真輝
今回私は、2024年12月9日から13日までシンガポールのMax Atria @ Singapore EXPOにて開催されたThe 12th Singapore International Chemistry Conference (SICC-12) に参加しました。「Precision Synthesis of Peptide Chimera through Site-Specific Peptide N-Terminus–Dehydroalanine Cycloaddition」というタイトルで、近年、生命科学研究において注目されているペプチドの異種連結体であるペプチドキメラの新規合成法の開発についてポスター発表を行いました。
本学会ではアジアの著名な研究者や新進気鋭の若手研究者が集まっており、聴講した講演では各講演者の研究の展開力と周辺分野を網羅的に探索していくスピード感に圧倒されました。
私が今回の学会で得られた成果は主に2つあります。1つ目は海外の研究者と英語で議論を行えたことです。私は、英語を話すことに対して苦手意識がありました。研究室の抄録会や研究の進捗報告会では英語を使用しますが、海外の研究者との会話や研究のディスカッションについてはほとんど経験がありませんでした。今回のSICC-12への参加が決まったときも、嬉しいという感情よりも、日常会話もままならないのに、化学のディスカッションなど不可能なのではないか、参加して大丈夫なのだろうかと不安を感じました。当日、実際に自分のポスターを見に来てくださった海外の研究者の方とディスカッションしてみると、ポスターに書いてある構造式やデータなどを介せば、拙い英語でも研究に関する議論がある程度成立することを体感しました。質問された内容が部分的に聞き取れず、何度か質問し直したりして苦戦をする場面もありましたが、事前に用意した補助資料等も用いて説明した甲斐もあり、最終的には多くの人に理解して頂けたと思います。また、有機合成化学以外の研究分野の方とも議論する機会があり、自分とは違った視点でのコメントを頂くことができ、大変勉強になりました。
2つ目は現地の文化を知れたこと、実際に現地の人と交流できたことです。私はこれまでに国外では韓国と台湾に行ったことがあり、シンガポールも同じアジアだから似たような雰囲気の国かと思い込んでいましたが、想像とは大きく異なりました。最も印象的だったのはシンガポールではキャッシュレス化がかなり進んでいたことです。特に、MRTという地下鉄に乗る際には、日本のような1回きりの切符ではなく、基本的に専用のICカードを購入、必要に応じてチャージする必要がありました。学会初日にICカードのチャージでトラブルが起きてしまい、途方に暮れていたのですが、通勤の時間帯にも関わらず、現地の住人の方が丁寧に教えてくださり、無事学会の会場に行くことができました。また、学会期間中に会場近くで昼ごはんを食べた際に、店員の方が気さくに話しかけてくださるなど、シンガポールの現地の方と交流させて頂くことができました。これらの一連の経験を経て、英語を話すことに対する抵抗も減らすことができたと思います。
最後に、この度、シンガポールの学会に参加するにあたり、渡航費・滞在費などの経済的なご支援をして頂きました齊藤宏様・和子様ご夫妻に厚く御礼申し上げます。今回の学会は長期間の滞在であったことや航空機代、学会参加費も高額であったことから、齊藤記念薬学教育研究支援基金によるご支援がなければ、このような貴重な経験はできなかったと考えています。今回の経験を糧に博士課程ではさらに精進したいと思います。
- 合成制御化学分野
- 博士課程前期2年の課程 2年次
- 渡邊 凌
今回私は10月2日〜4日に米国Rice大学主催でフランスのパリで開催されたThe Art and Science of Total Synthesis of Natural and Designed Molecules for Biology and Medicine (ASTS-NDM 2024)に参加し「Development of BRD4 Degraders: Two-Phase Strategy with The Alkyne-Modified TK-285」というタイトルで、近年注目を集めるモダリティであるPROTACの独自の戦略に基づくBRD4分解誘導剤の開発についてポスター発表を行いました。本国際会議はノーベル賞受賞者を含む世界トップクラスの講演に加え、参加人数が100人ほどと比較的絞られているため親密な交流が可能でした。そのため国際感覚の獲得や交流に有意義な機会となりました。普段論文で目にする著名な先生の講演を実際に聞くことで非常に刺激を受け、今後の研究へのモチベーションも向上しました。
今回の経験を通じて以下2点の成果が得られたと感じております。
1点目は海外の方と交流することや、英語を用いて発表及び議論することへの抵抗感を払拭できたという点です。私自身これまで海外での国際会議参加はおろか海外渡航の経験もなかったため、参加以前は不安を抱えていました。しかし、拙い英語ながらも自身の研究内容や発表者との議論が可能であることを経験し、簡単な英語でも伝える意思があり、単語と文法があっていれば伝わることを実感し、積極的にコミュニケーションを図る姿勢が重要であることを強く感じました。
2点目は、自身の視野が大きく広がったという点です。海外の学生と直接話す中で、キャリアについて国境を越えた多様なプランを考えていることを知り、刺激を受けました。日本という限られた環境で物事を考えていることを改めて実感しました。
また、今回の渡航を通じて、研究力があり、英語が話せれば世界中の研究者と自由に議論できることを強く実感しました。今後は自分の選択肢を広げるために、研究と並行して英語力の向上にも励みたいと思います。
今回の国際会議への参加を通じて、自身の研究力及び英語力の未熟さを痛感しました。初の国際会議参加ということで0から1の貴重な経験をさせていただいたので、博士課程進学後は今回の経験を1から100に成長させ、世界で活躍できる研究者になるため日々の研究活動に邁進していきたい所存です。
最後に、渡航費などの経済的な支援をいただきました齊藤宏様、和子様に厚く御礼申し上げます。
.png)